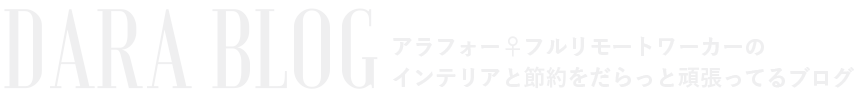大阪マラソンの募集が締め切られましたね!私すっかり応募を忘れてまして、人生発のフルマラソン完走を逃してしまったんですが、調べてみたらその前の週に大阪ハーフマラソンっていうのがあるじゃないですか!
ハーフの方が気軽だし、やってみたい!と応募フォームにポチポチと入力したら、大阪ハーフマラソンってハーフを2時間で切らないとDNFになっちゃうってこと初めて知りまして、ハーフを2時間ってことは1km6分切るペースで走らないとダメってことなの?無理じゃない??でも大阪走ってみたいしハーフ出たい!!って今なってるところです。

大阪ハーフマラソンとは

大阪ハーフマラソンとは、新春に大阪の市街地を走る、距離21.0975kmのハーフマラソン大会で、大阪国際女子マラソンと同日開催されます。2026年は1月25日開催、大阪城公園をスタートし、ヤンマースタジアム長居でフィニッシュする、フラットで記録の出やすい高速コースが特徴です。女子マラソンとコースを一部共有するため、レース中にトップ選手とすれ違うことができるという走るのも観るのも楽しそうな大会です。
しかし、大阪マラソンは競技制を重視した大会のためめちゃめちゃ厳しい大会とも言われており、制限時間が2時間、1kmあたり6分を切れるペースで走る総力が必要。レベルでいうと中級者から上級レベルの猛者ばかりが参加しているそうです。
だらもとのマラソン歴と走力について

だらもとは今年の1月ぐらいからランニングを始め、月50〜80kmぐらいを走っていて、これまでの最長は12km。10km大会にようやく出れるようになったレベルで、夏の大会で10km59分で走り切りましたがまだまだ「やっと」っていう感じです。
ChatGPTに2時間走り切れるか、聞いてみた。
ChatGPTに今日までの大会記録や月毎の走行距離を渡して、大阪ハーフマラソンを走り切れるか聞いてみました。
今のペースで練習を積めば、2025年12月時点で10km=55分前後、
その状態で臨めば2026年1月の大阪ハーフで1時間55分前後が十分狙えます。
…どうやら、AIは走れると予想してます(ほんまかいな)
どんな練習を積めばいいのかも聞いてみました↓
🔹ロング走(15〜20km)の習慣化
月2〜3回、ペースを落として長く走る。徐々に距離を伸ばすことで後半も足が動くようになります。🔹ペース走(6:00/km→5:40/km)
最初は6:00/kmで10〜12km走り、徐々にレースペース(5:40/km)に近づけていく。🔹スピード強化(インターバル・ビルドアップ)
短い距離で速く走る練習を週1回入れると、巡航ペースが楽に感じられるようになります。🔹月間走行距離を80〜100km台で維持
急増は故障のもとですが、秋〜冬は80km以上をキープできると安定感が増します。
こんなもんで本当に2時間切れるのかは謎なんですが、目安としては覚えておこうと思います。
フルマラソンをサブ3で走る彼氏に「大阪ハーフマラソン出たい!」って言ったら「無理だと思う」と苦笑いでした。こっちの方が、リアリティある…
課題とこれからのランニングのメニューについて
長い距離を走ったことがない、早く走れないは常に私にある課題ですが、体調面でも課題というか不安がありまして
- 長い距離、頻度高く走ると膝が痛い
- 親指の爪が剥がれそう
- 体が硬い、特に肩が走ってて違和感あるぐらい硬い
この辺りをカイゼンするために、筋トレやストレッチをランニングとは別にやっていきたい所存です。
ランニングのメニューについてはChatGPTに相談しつつ、
- 9月中に15kmをゆっくり走る
- 10-11月に20kmを2-3回走る
- たまにスピード練習する(どうやるかは今後調べる)
こんな感じで3ヶ月ぐらいやっていこうと思います。ハーフマラソンの大会どこかで出ておきたいな。
現時点無理そうも、大阪ハーフマラソンを目標にする

今年1月に走り始めて、その時は1kmも走れなかったのに今やハーフマラソンに挑戦したいと思えるぐらい成長してて自分でもびっくりしています。
大人になってこれほどのめり込む趣味みたいなのもなかったので、体力が許す限りはたくさん頑張っていきたいです。
大阪ハーフマラソン、もし無事完走できたら一緒にお祝いしてください☺️☺️